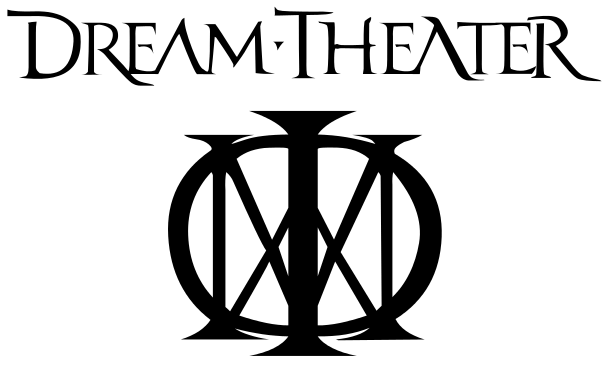Metropolis Part 2: Scenes from a Memory (1999)
(1999)

新加入キーボード、ジョーダン・ルーデス(ハゲ)(当時は髪あり)を迎え製作されたアルバム。
2ndアルバムの一番人気があったと思われる曲Metropolis Part I: “The Miracle and the SleeperのPart2としてアルバム制作。一枚のコンセプトアルバムとして展開。
この1992年発表曲を元ネタとして、新アルバム全体にそれぞれ以前のフレーズや歌詞が仕込まれているおもしろい内容。
当時のファンは感動しました。新キーボードのジョーダン・ルーデス神(髪)かよと。
俺らの求めてたDREAM THEATERが帰ってきたぞ、と。
ボーカルのジェイムズ・ラブリエも新しい発声が板についてきて好調そうだなと、当時の私は安心しました。
未だにDREAM THEATERのアルバムでも上位の人気を誇る作品だと思われます。
完全再現ライブは印象的でした。
前任キーボードのデレク・シェリニアン在籍時のレアデモ音源。
Six Degrees of Inner Turbulence (2002)
(2002)

初の2枚組フルアルバム。
キーボードのジョーダン・ルーデス(ハゲ)が本領発揮し始めます。
テーマ的に重い内容を扱っているものの、全体的にサウンド自体は細やかで繊細な印象はあります。
前作のアルバムのラストから通して聴くと、今作につながっているような1曲目からの演出が当時エモかったですw
ついに人気も上がり続け、武道館ライブをやるまでになりました。
ギターのジョン・ペトルーシが一番イケメンギタリストだった時代でもあります。
(今は太ってるかつ筋肉オバケ、汚いロン毛に髭)
当時のこの映像みてくださいよwwwスラッとしてイケメンやないですかw
Train of Thought (2003)
(2003)

前2作が比較的明るめタッチのサウンドだった反面、今作は全体的に異常なヘヴィさを押し出した作風。
個人的にHonor Thy Fatherという曲が好き。
インスト曲のなかでもStream Of Consciousness(通称ストコン)は楽器やる人間に大人気な一曲。
ジョン・ペトルーシのイケメン時代継続。
2004年にはクビになったボーカル(チャーリー・ドミニシ)とキーボード(デレク・シェリニアン)の一夜限りの競演が果たされる。
このライブ見に行けた人はマジ羨ましい。
Octavarium (2005)
(2005)

俺的超名作アルバム。DREAM THEATER的プログレここに極まれり。という感想。
最初の曲「ザ・ルート・オブ・オール・イーヴル」は前作の最後の曲「イン・ザ・ネイム・オブ・ゴッド」の最後でジョーダン・ルーデスが鼻で演奏したピアノの音から始まっており、『メトロポリス・パート2: シーンズ・フロム・ア・メモリー』から続くアルバムの最後の音が次作の最初の音と繋がるパターンを踏襲している。ただしこちらのパターンは本作で完結している。アルバムの全曲は異なった短音階で、F(ヘ短調)から始まり、それからG(ト短調)、A(イ短調)、B(ロ短調)、C(ハ短調)、D(ニ短調)、E(ホ短調)と続き、そしてF(ヘ短調)に戻る。これは、ライナーノーツ中のト音記号横の調号で明らかである。また、曲の組の間、すなわちCDにおいて先行する2番目のペアの曲での負の時間として表現される境界部(変わり目)は、それぞれのペアと関連付けられた臨時記号の一致によって作られる。例えば、「パニック・アタック」で続くシンセサイザーのソロ(ハ短調)は、次の曲の「ネヴァー・イナフ」(ニ短調)での負の時間として位置し、嬰ハ短調(C# minor)である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
特にアルバムタイトル曲のOctavariumは狂気すら感じる至高の一曲。
Systematic Chaos (2007)
(2007)

このアルバムからドラムのマイク・ポートノイが新しい実験をいろいろやりたかったことが伺える作風に変わってくる。
より現代風ヘヴィ要素を取り入れようとしたりしている。
ヘタクソな本人のコーラスいたるところに入れたりして、求めていないファンからすると「コレジャナイ」感のあるアルバムに仕上がっていた気がします。
この頃から本格的に日本ではマイク・ポートノイはジャイアンと揶揄されるようになる。
Black Clouds & Silver Linings (2009)
(2009)

このアルバムを最後にバンドリーダー、ドラム、マイク・ポートノイが最終的に脱退することになる。
ファンの多くもマイク・ポートノイのやりたいこととバンドメンバーがやりたいことは乖離していただろうなと薄々気づいていたりもした。
ただ、リーダーが脱退となると「これもう解散じゃね?」という寂しさがあった。